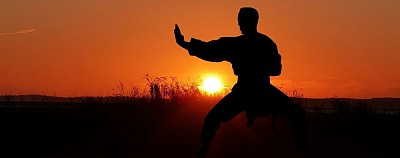空手の起源
明確な起源は判明しておりませんが、琉球王国時代の沖縄発祥と言われております。古来から沖縄にあった武術の手(テイ)に中国(唐)の拳法が融合して独自に発展したという見方が一般的です。沖縄では今でも空手ではなく唐手とする団体も多く見られます。
大正時代に沖縄県出身の空手家達が本州に渡り他の都道府県に伝えました。その後、昭和に入って日本の武道として正式承認を受けることとなります。
現在普及している空手道は、古来の技術と鍛錬法を代々受け継ぐ沖縄系空手、オリンピック等の公式ルールに基づいた素手技と型の鍛錬に特化させた伝統空手、新たなルールによって独自発展したフルコンタクト空手などがありますが、源流を辿るとすべて同じです。
今日の空手道は打撃と避け受けを主体とする格闘技でありますが、古来の空手には関節技や投げ技や掛け・掴み技も含んでおり、その名残が型に多く残っております。また、素手技以外に棒、釵(サイ)、ヌンチャク、鎌、トンファといった武器術も併せて修行したものですが、現在では素手技に特化したものとなり、武器技を伝承する団体は少数派となりました。沖縄県内では今でも広く伝承されております。
多くの流派が存在しておりますが、一般的に主流とされる四大流派は剛柔流・糸東流・松濤館流・和道流です。沖縄空手においては小林流、上地流も広く知られております。沖縄空手と伝統空手は共通点も多く区別が難しいかもしれません。フルコンタクト空手は戦い方からルールまで異なり独自発展しておりましたが、近年は伝統空手の型も積極的に取り入れるようになっております。